前回のコラム(https://x.gd/sZgCb) で、作成したブランド・商品コンセプト案の消費者への魅力度評価法をご紹介しました。
では、その消費者に確認する前に、そもそも「独自性のある便益」のあるブランド・商品コンセプト案はどのように開発・作成すればいいのでしょうか?

新商品のコンセプト案開発においては、
「POSでいま売れていたり、SNSで話題の商品の改善・延長線上で発想する」
「流通のバイヤーから打診・依頼のあった方向性で考える」
「商品企画などの部署でブレストしてひねり出す」
「外部のコンサル・アドバイザーに依頼する」
…などがよくあるケースかと思います。
でも実は、その企業の社員(商品企画や開発・マーケティング関連部署だけではない、製造や営業や総務や人事やITなども含めた様々な部署)の皆さんの心の中に、色々な可能性のある商品コンセプトのヒントが存在していることが多々あります。
そしてそれを自発的に、かつ各案が比較しやすい形で活発に出てくるようにする、ということは「ちょっとした工夫」をすればそれほど難しいことではないのです。

その「ちょっとした工夫」とは、主に以下の3つです。
- (専門家ではなくても理解できる)現状の環境分析の情報共有
- (様々な案を出しやすくする)コンセプト案の募集・提出方法
- (各案の比較をしやすい)コンセプト案フォーマットの統一
今回は、まず上記の1番目について。
1. (専門家ではなくても理解できる)現状の環境分析情報の共有
- これは、簡単に言うと『企業やブランド、商品カテゴリーにおける「課題」と「伸びしろ・チャンス」を専門部署の人以外でもわかりやすいように、かつ簡潔にまとめたもの』です。
※これはもちろん、ブランド・商品コンセプト開発だけでなく、通常のビジネス戦略作成においても基本となるアクションです - 「なぜ課題と伸びしろ・チャンスを他部署の人にもわかりやすいようにしなければならないの?」という理由は、
『自分達の企業やブランド、商品カテゴリーにはどのような課題や伸びしろ・チャンスがあるのか、をわかりやすい客観的な事実やデータ(ユーザーや関係者の声も含む)などで把握することで、参加者各自が専門的な知識がなくても自分ごととして認識でき、新しいコンセプトの出発点となる土台の共有・目線合わせができるから』
ということになります。
※「課題」は裏返せば「伸びしろ」ですので、顧客起点で考えた時にここが何なのか、を深掘りすることはとても大切です!

- その中でも、特に前々回のコラム(『誰かの「フツー」は、他の人にとっての「インサイト」(かも)』 https://x.gd/FtPY3)にも記しましたが、「N1」、ユーザーや関係者の生の声を深掘りして聞いていく、ということはとても重要となります。
もちろんPOS等の様々な定量的なデータから傾向を探ることも大切ですが、そのようなアプローチは得てして
『最大公約数』的な発想(=「いまこれがウケているからやる」「多くの人がそうしているからやる」というような、何かあった時に言い訳ができるもの)
になりがちで、
「独自性のある便益」
の発見・構築にはつながりにくいこともあるため、それだけに頼るのは要注意です。

- そして、これをメンバーや関係者に理解・納得してもらうためには、例えばフレームワークとして、SWOT・クロスSWOTや、それを作るためのPESTや5-Forceや3Cなどを活用してもいいのですが、その場合は以下a、b、c に注意することも大切です:
- 環境分析を完璧に作ることに多大な精力と時間を(場合によっては費用も)使い、フレームワークを作ること自体が目的化し、実際の案の作成時には息切れしてしまう(=「分析はもっともなんだけど、で、出てきた案がこれ?」ということになりがち)

- 様々なフレームワークを一度に見せられると、専門知識のない人たちにとってはかえってわかりにくくなり、また理屈っぽく面倒くさそうなイメージを与えてしまうと、その人たちのコンセプト案作り参加へのモチベーション自体にも影響しかねない
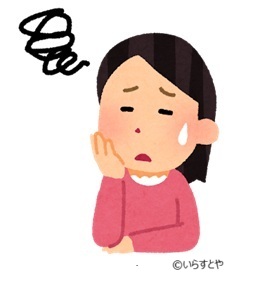
- SWOTにしても、S(強み)とW(弱み)は表裏の関係にあり、同じ事象・要素であっても見方によってどちらにも捉えることができたりもするので流動的な部分が大きい(なのに、それを固定したものとして捉えてしまうと、「逆張り」とか「広く浅く受けるものよりも狭く深く刺さるものを」というような選択肢が考えにくくなる)

※マーケティングで使う各種のフレームワークに関しては色々なところで紹介されていますが、参考までに以下Salesforceのリンクを:
『マーケティング分析の10種類のフレームワークのやり方や手順を解説』 https://www.salesforce.com/jp/resources/articles/marketing/marketing-analysis/
さて、『「課題」と「チャンス」を専門部署の人以外でもわかりやすいように、かつ簡潔にまとめる』ことができたあと、メインとなる2番目、『(様々な案を出しやすくする)コンセプト案の募集・提出方法』に進みます。こちらは次回、具体的な手法(費用はかからず、特別なシステムを導入する必要もなく自分達でできるものです)の紹介を含めて説明させていただきます。

